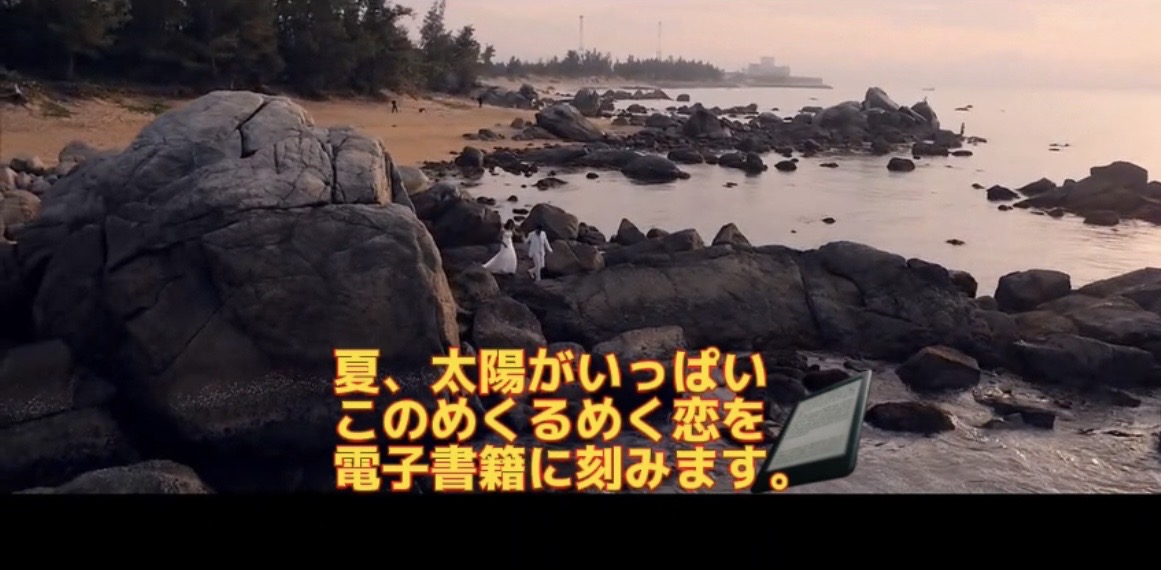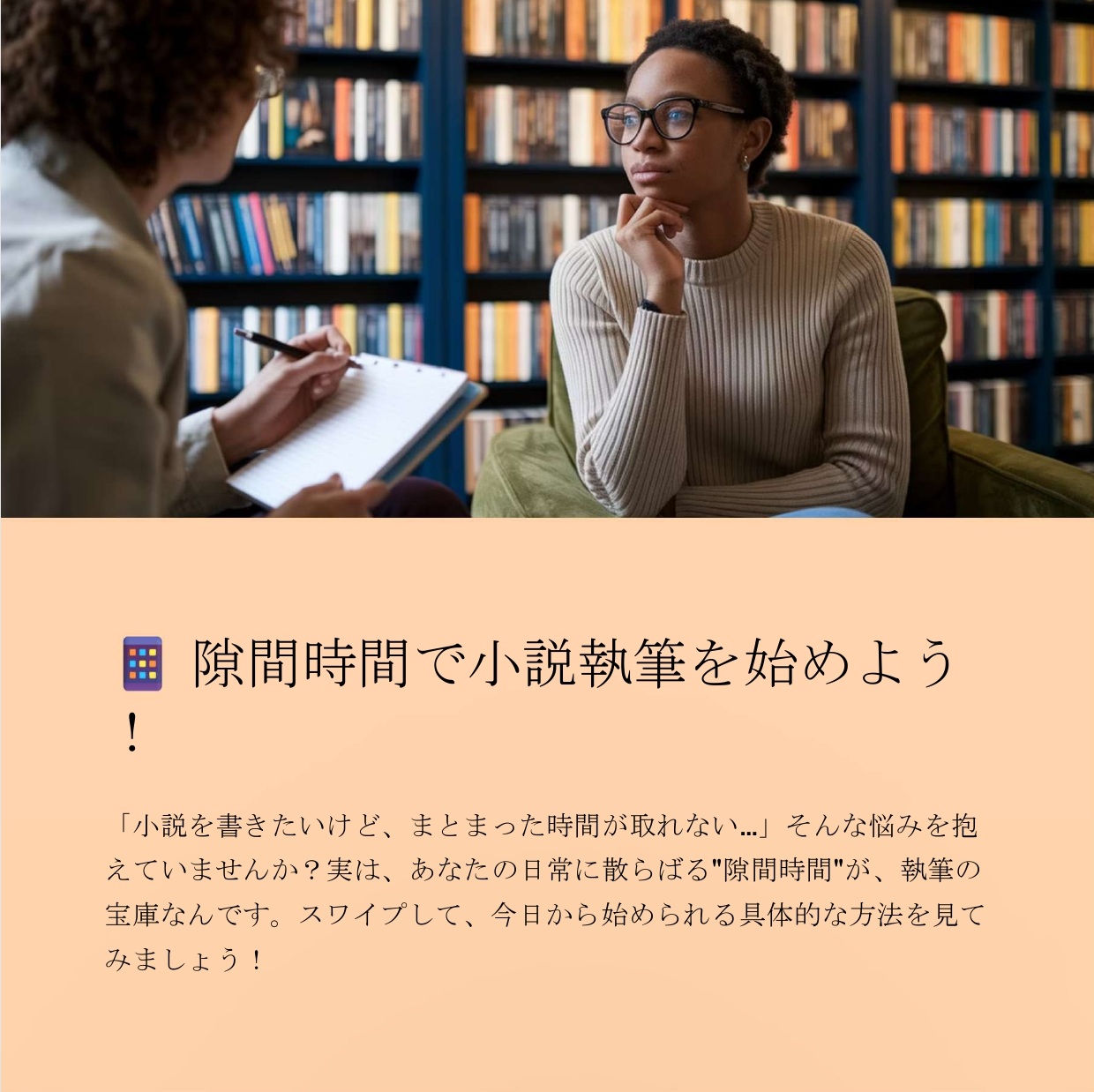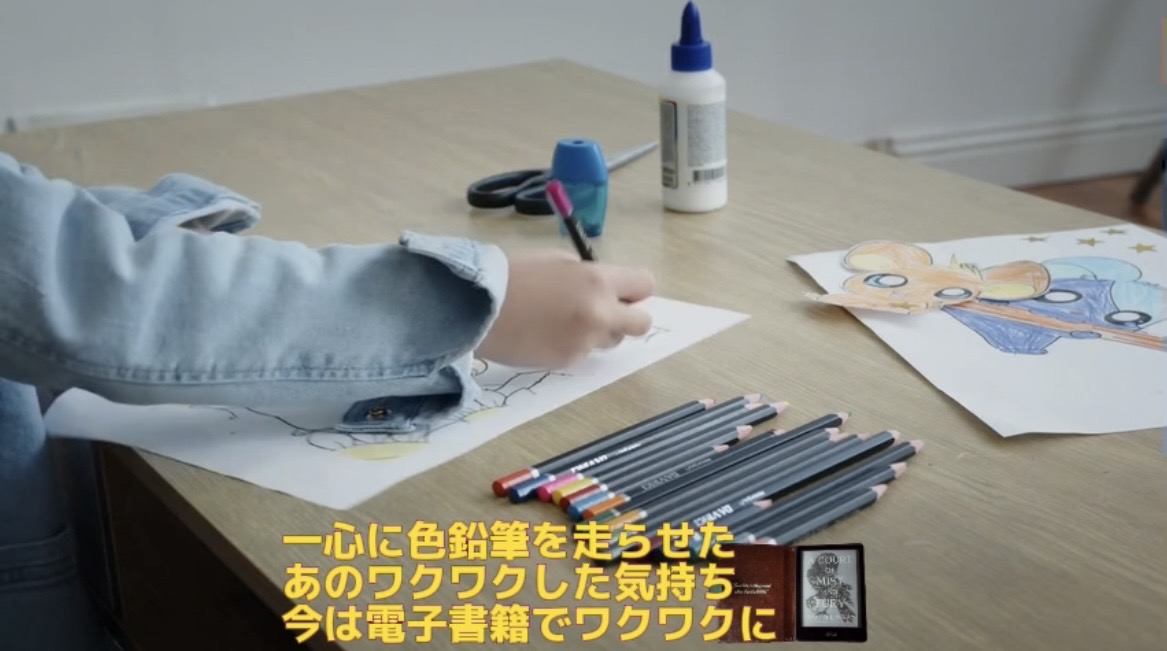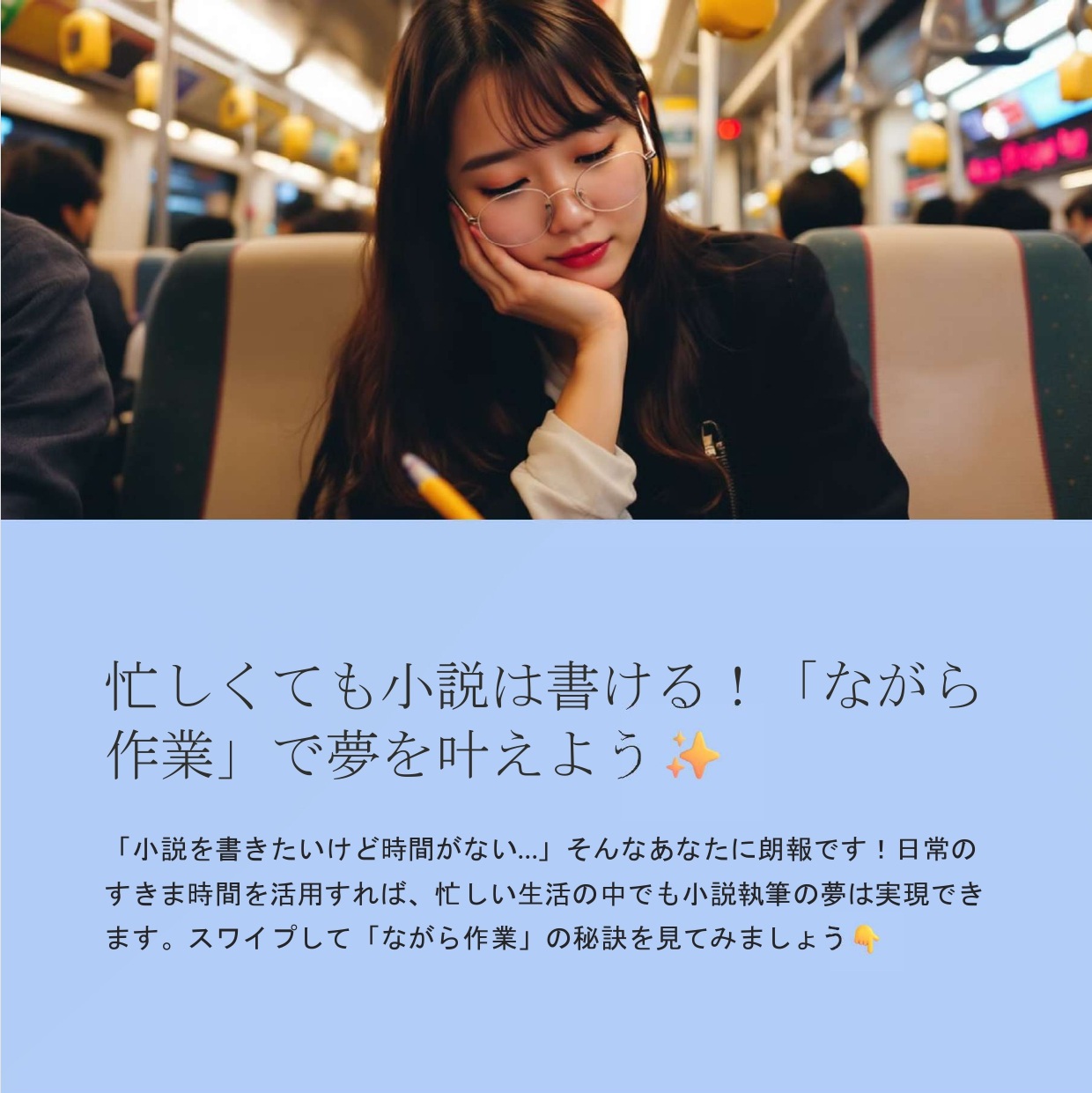「実用書の価値を高める!読者の行動を引き出す文章術」

はじめに
アナタは、実用書を書いた経験がありますか?
せっかく時間をかけて丁寧にまとめた内容でも、読者が何も行動しなければ、その本はただの「読んだだけの本」になってしまいます。
でももし、アナタの書いた文章が読者の背中をそっと押して、「ちょっとやってみようかな」と思わせられたなら、その本の価値はぐっと高まります。
この記事では、読んだ人が自然と行動に向かう文章の書き方を、わかりやすく紹介していきます。
読者が動かない理由を知る
読者が動けない一番の原因は、感情に火がついていないからです。
アナタが伝えた知識がどれだけ役に立つものでも、読む人の心に響かなければ、実際に動いてみようとは思ってもらえません。
アナタの文章には、
- やってみたら良いことがある、と感じさせる「ワクワク感」
- このままではもったいない、と気づかせる「もやもや感」
こうした感情のきっかけが、きちんと入っているでしょうか?
人の行動は、頭ではなく「心」が動いたときに始まります。
行動につながる3つの工夫
アナタの文章に、次の3つの要素を入れることで、読者が動き出す可能性はぐっと高まります。
ひとつずつ、見ていきましょう。
ひとつ目 具体的なメリットをはっきり伝える
読者は、「自分にどんな良いことがあるのか」を知りたいのです。
たとえば、
「この方法を試せば、月3万円の節約になる」
こう書けば、数字が入っているぶん、イメージしやすくなります。
アナタの文章は、読者の生活の中に「変化」が生まれることを、はっきりと示せているでしょうか?
ふたつ目 やるべきステップを小さく分ける
「まず朝起きたら〇〇をする」
「次に出かける前に△△をしておく」
このように、一歩ずつやることが分かれば、読者は「これならできそう」と感じます。
最初からゴールを見せるのではなく、小さな一歩を一緒に踏み出せるような言い方が、アナタの文章に求められます。
みっつ目 行動後のイメージを描かせる
たとえば、
「この習慣を取り入れると、毎朝ゆっくり朝ごはんを楽しめるようになる」
読者は、自分の未来を頭の中に思い描いたとき、「やってみようかな」と感じます。
アナタの書く文章は、読者にそのイメージを見せていますか?
言葉の選び方がカギになる
読者が自然と動きたくなるような言葉には、いくつかのポイントがあります。
まず、「アナタも今日からできる」
このように、読者が主役になるような言い方が効果的です。
また、「〜すべき」といった言い切りよりも、
「〜してみるといいかもしれません」
というやさしい言い方の方が、読者の気持ちを動かしやすくなります。
アナタの言葉は、命令ではなく、寄り添うようなトーンになっていますか?
行動につなげる文章の流れ
文章全体の流れにも、ちょっとした工夫が必要です。
読者にとって読みやすく、そして実際の行動へとつながる構成は、次の順番がとても効果的です。
- 悩みを提示する
読者が「これ、自分のことだ」と思えるような問題を取り上げる - アナタの考える解決策を出す
その問題に対して、どうすればいいのか、アナタの経験や知識を伝える - 具体的な行動を示す
すぐに試せる小さなステップを紹介する - 実行したあとの良い変化を描く
その行動のあと、どんな気持ちになれるか、どんな日々が待っているかを描く
この流れを意識すれば、アナタの文章は自然と読者の背中を押せるようになります。
読者を思い浮かべて書く
どんな人に向けて書いているのか、アナタははっきりとイメージできていますか?
- どんな毎日を過ごしているのか
- どんなことで困っているのか
- どこまでの知識があるのか
これを想像しながら書けば、アナタの言葉はぐっと届きやすくなります。
さらに、読みやすさも忘れてはいけません。
- 文章は短めにまとめる
- 必要な情報は箇条書きにする
- イラストや図で伝えるときは、できるだけシンプルに
こうした工夫で、読者はストレスを感じずに読み進められます。
おわりに
実用書の本当の価値は、アナタが伝えたい知識ではなく、「読んだ人が動いて、良い変化を感じられるかどうか」にあります。
この文章術をアナタの書く本に生かせば、読者はページを閉じたあと、自分の生活を少しずつ変え始めてくれます。
そして、「この本、すごく良かったよ」と、誰かに伝えたくなるのです。
アナタが届けたい言葉が、誰かの行動のきっかけになる――そんな一冊を、今日から目指してみませんか?