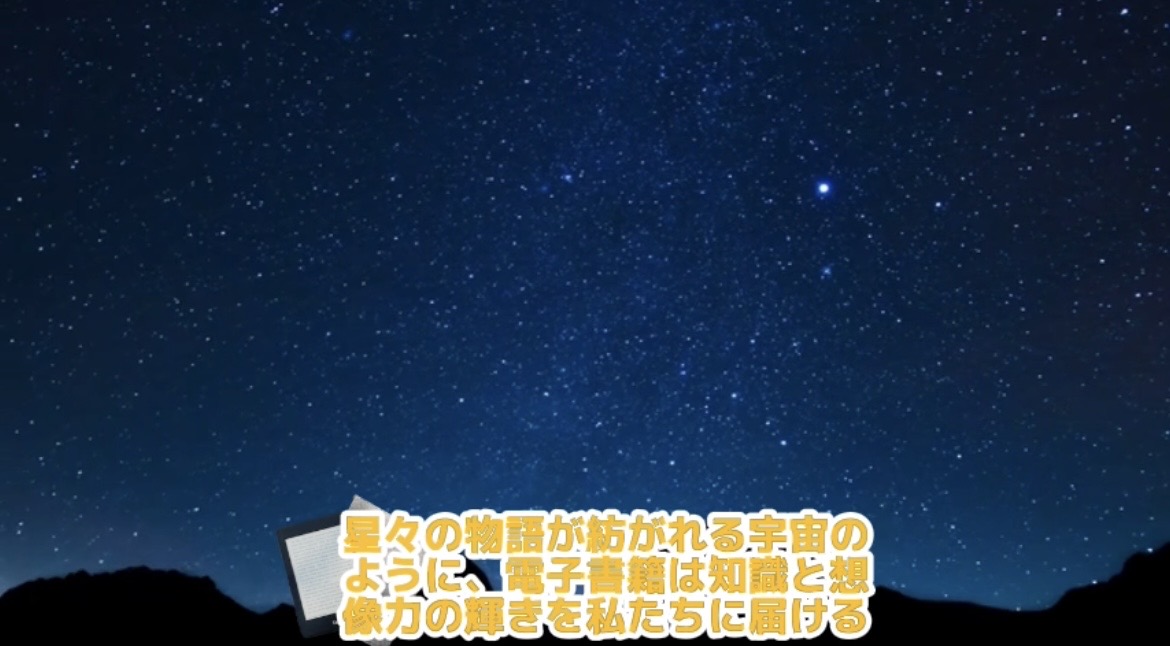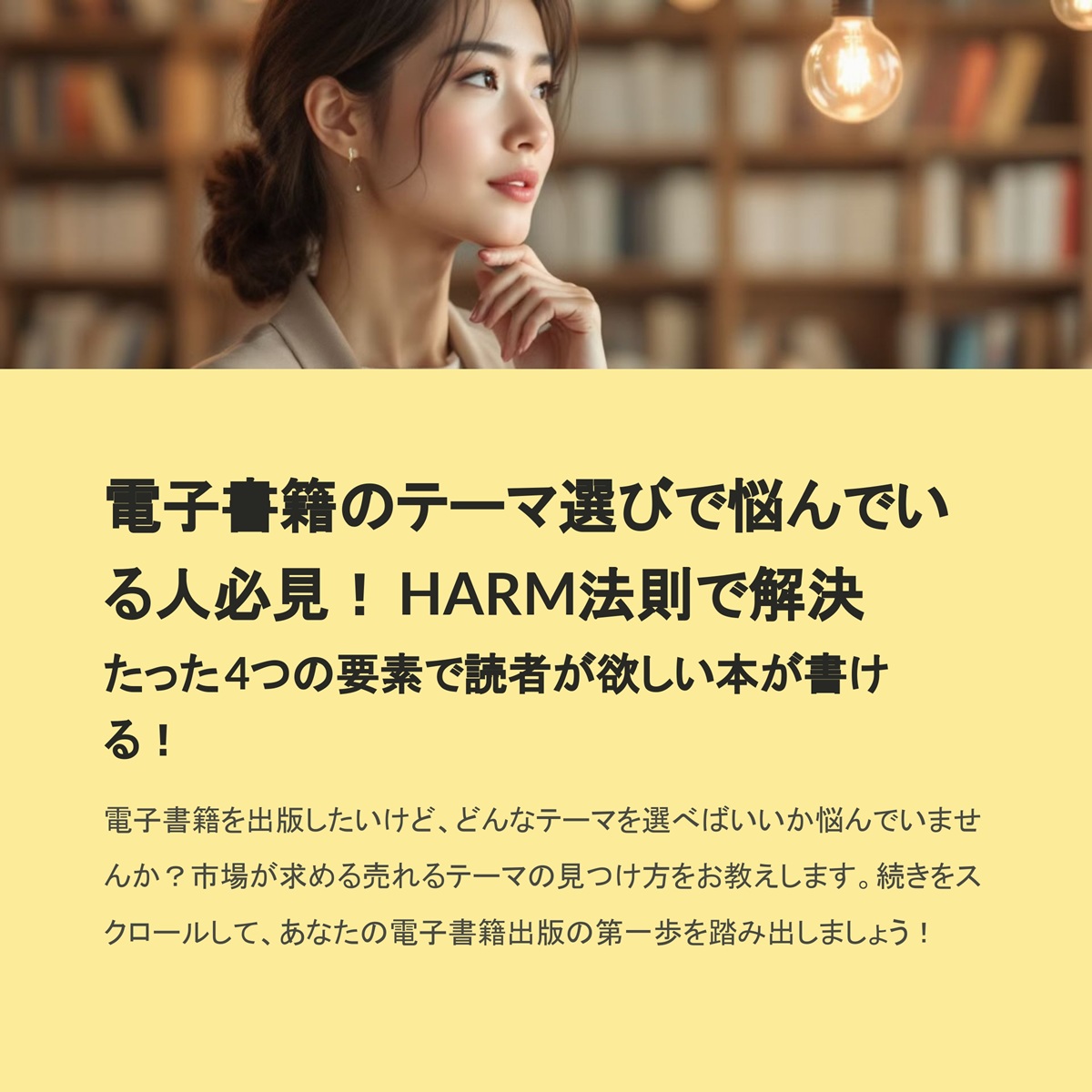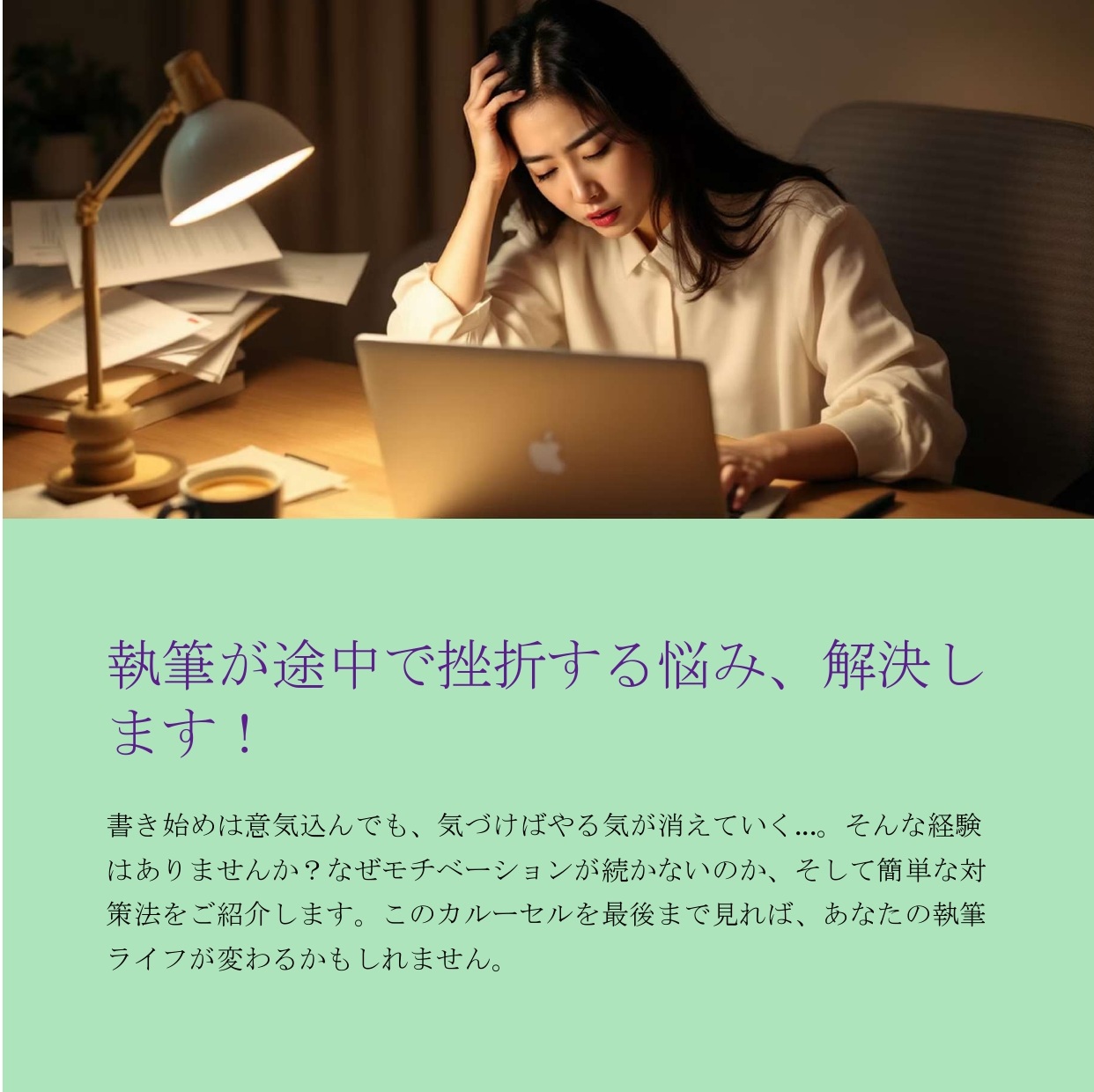「📘 実用書を出版したのに読まれない…その理由と読者に届けるための5つの実践術」

はじめに
「実用書を書いたのに、誰にも読まれていない気がする」
そんなふうに感じて、ひとりで胸がギュッと締めつけられるような思いをしているアナタへ。
実はそれ、多くの実用書著者が最初にぶつかる“壁”です。けれど、それは決してアナタの本に価値がないからではありません。
むしろ逆です。中身には十分な価値があるのに、「届け方」でつまずいてしまっているだけなんです。
この記事では、そんな“もったいない”状態を抜け出すために、
出版したばかりのアナタがすぐに実践できる「届けるための5つの方法」を、具体的な例とともにお届けします。
読み終わるころには、「自分の本を、誰に、どうやって届ければいいのか」が、クリアに見えてくるはず。
さあ、アナタの本当の力を必要としている読者へ。
アナタの言葉を、今ここから、ちゃんと届けていく一歩を一緒に踏み出しましょう。
1 読者の悩みとズレていない?
「この本は、誰の、どんな悩みを解決するためのものなのか?」と聞かれて、アナタは即答できるでしょうか?
実用書がなかなか読まれない大きな理由のひとつが、「届けたい相手像」があいまいなままになっていることです。
たとえば──
・毎朝、家族の支度に追われてバタバタしているワーキングマザー
・片づけが苦手で、部屋が物でいっぱいになりがちな一人暮らしの男性
・定年後に新しい挑戦として副業に踏み出そうとしている60代の女性
こうした具体的な読者像が浮かんでいないと、「この本、なんだか自分には関係なさそう」と思われて、読み飛ばされてしまいます。
アナタの本が本当に届くためには、
・読者が“今どんな場面で、どんな気持ちで困っているか”を丁寧に想像し、
・その悩みを、まるで本人の口ぐせのように会話調で書き出してみる
・「読者がどんなキーワードで検索するか」を逆算して、タイトルや章の見出しを見なおす
こうした工夫がとても重要になります。
読者の悩みを“先回りして言葉にする”ことが、「あ、この本、自分のことをわかってくれてる」と感じてもらえる、最初のカギなのです。
Q ターゲットを絞ると読者が減るんじゃ…?
A いいえ、むしろその逆。深く刺さった本は、「これ、あの子に読んでほしい!」と自然に広がっていきます。
2 「読んだあと、どうなれるか」が見えている?
人は本を手に取るとき、無意識にこんなことを考えています。
「この本を読んだら、自分はどう変われるんだろう?」
それが見えないままだと、どんなに中身が優れていても、「また今度でいいや」と思われてしまいがちです。
だからこそ、こんな表現が読者の心を動かします。
・「3日坊主でも続けられる“朝5分”習慣」
・「冷蔵庫が片づいたら、食費が1万円減った!」
・「もう“時間がない”とは言わなくなる、超シンプル時間術」
アナタの本が届ける「変化」は、読者にとっての小さな希望であり、大きな一歩になります。
・読者が「できるようになった自分」を想像できるような表現を選び、
・数字や期間など、明確なゴールを提示し、
・読むごとに少しずつ“できた!”が重なっていく構成を目指してみてください。
そして──
出版後のアナタ自身にも、変化が訪れます。
「読んだよ」という感想が届き、自信が芽生え、
SNSで紹介される喜びに胸が躍り、
気づけば、次の本にしたいテーマが自然と浮かんでくるようになります。
「一冊出したら、世界が変わった」
そんなふうに語る著者が多いのは、決して大げさではないんです。
Q 「読後の未来像」って本当に必要?
A それこそが、読者の心をグッと引き寄せる“読む理由”になります。
3 情報を詰め込みすぎていない?
ありがちな失敗のひとつが、「あれもこれも伝えなきゃ」と、情報を盛り込みすぎてしまうこと。
でも、実用書で本当に評価されるのは、「情報の量」ではなく、「情報の届け方」なんです。
たとえば──
・伝えたいことが多すぎて、章が10以上に細かく分かれてしまったり、
・目次がズラリと長く並んで、読む前にお腹いっぱいになってしまったり、
・テーマがあちこちに飛んで、読者が迷子になってしまったり。
こんな状態では、どんなに役立つ内容でも最後まで読まれません。
・1冊につき、伝えたいメッセージは「ひとつ」に絞る
・深く語りたいテーマは、思いきって“次回作”に取っておく
・章立ては「悩み → 気づき → 実践 → 結果」と、読者の心の流れに沿って構成する
読みやすい本は、それだけで「この本、最後まで読めた!わかりやすかった!」という満足感を生みます。
Q せっかく書いたのに削るなんて、もったいない…?
A 削ることは、アナタの優しさのあらわれ。“読みやすさ”は、最高の読者サービスです。
4 発信を後回しにしていない?
「本は出した。あとは売れるのを待つだけ」
もし、そんなふうに思っているなら──ちょっと立ち止まってほしいのです。
なぜなら、本は“出した瞬間”が、スタート地点だから。
たとえば、
・本屋に並ばず、広告も出されず、誰にも紹介されていない電子書籍
・せっかく書いたのに、SNSでもブログでも何も語られていない一冊
それは、せっかく仕上げたアナタの本が、ひっそりと眠ってしまっている状態です。
届けるためには、アナタ自身の“声”が必要です。
・SNSで「なぜこの本を書いたのか」「誰に届けたいのか」を語ってみる
・届いた感想やレビューを紹介しながら、「読んだあとのリアルな変化」を共有する
・noteやブログで、内容の一部を“実践記事”として公開する
たとえば、「この本のおかげで朝5時に起きられるようになりました!」という声が届いたら、
それを紹介するだけで、新しい読者は「自分もできそう」と感じてくれます。
Q 発信って苦手でもやったほうがいいの?
A はい。たった一言でも、アナタの声は“人”として、読者の心にちゃんと届きます。
5 届けるための道筋を設計している?
実用書は、ただ書くだけでは読まれません。
「どうすれば読者に気づいてもらえるか」を考えて、届けるための“道”を設計する必要があります。
それは、「売る」というより、「気づいてもらう仕組み」をつくるということ。
たとえば──
・SNS投稿のタイミングを、読者が最も見ている時間帯に合わせる
・noteで連載形式にして、物語のように少しずつ届ける
・Kindle Unlimitedに登録して、まず“試し読み”できる間口を広げる
そして、「どんなテーマが求められているの?」と悩んだときには、以下のような例も参考になります。
・朝の支度を整えるルーティン
・冷蔵庫の整理術
・子育て中のちょっとした声かけの工夫
・スマホとの付き合い方を見なおす方法
・実家の片づけを始めるための第一歩
・副業としてのハンドメイド販売の始め方
・40代から考える暮らしとお金のプラン
アナタが「これ、みんな当たり前に知ってるでしょ?」と思っていることこそ、
誰かにとっては「やっと見つけた!」と思ってもらえる、かけがえのないヒントだったりします。
Q じゃあ、その届ける仕組みって、何から始めたらいいの?
A まずは「読者がどこで出会ってくれそうか」を想像し、そこにアナタの言葉を置いてみるところから始めましょう。
おわりに
アナタの実用書には、ちゃんと意味があります。
それを必要としている誰かが、必ずいます。
読まれていないのは、アナタのせいでも、本のせいでもありません。
ただ、「届けるための準備」が、ほんの少し足りなかっただけ。
でも、大丈夫。
これからアナタは、自分の本をきちんと読者に届けられるようになります。
ほんの少しの工夫と、ほんの少しの発信。
それを続けていくだけで、読者から「読んでよかった」「ありがとう」という声が、届くようになります。
そして、その言葉がアナタにとって、次の一歩を踏み出す大きな力になるはず。
アナタには、もうすでに「届ける力」があります。
あとはそれを、信じて進めばいいだけです。
アナタの今日の発信が、明日どこかで誰かの心を救うかもしれない。
だからこそ、アナタのその一歩には、大きな意味があるのです。
 「誰でもできる!Kindle出版マーケティング入門」松尾 俊治(著)のご紹介
「誰でもできる!Kindle出版マーケティング入門」松尾 俊治(著)のご紹介
「Kindle出版、難しそう…」とためらっていませんか?
この本は、知識ゼロ・未経験でも、今日から始められるやさしい一冊。
ビジネスの集客や信頼アップのコツ、出版からプロモーションまでを丁寧に解説。
毎日が忙しい主婦やワーキングウーマンにもピッタリ。
一歩踏み出せば、あなたの想いが新しい価値として広がります。
さあ、「やってみたい!」の気持ちをこの本で形にしませんか?
※画像はイメージです